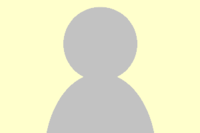- ホーム
- ブログ
ブログ
京都蹴上、ねじり鉢巻きでマンボを踊る?
2021/04/22京都に「蹴上」というところがあります。
読み方は「けあげ」です。
インクラインや浄水場や発電所があり、蹴上駅から南禅寺には歩いて行ける距離です。
- インクライン
琵琶湖疏水の大津から宇治川までの20.2㎞の舟運ルートの途中で水路の落差がある2カ所に作った傾斜鉄道です。
蹴上インクラインは延長581.8mで世界最長。

- 蹴上浄水場
日本最初のろ過式浄水場で、明治45年(1912年)4月から給水を開始しました。
- 蹴上発電所
琵琶湖から京都へ水を運ぶく「琵琶湖疏水」を利用した水路式水力発電所です。
日本初の事業用水力発電所で、明治24年(1891年)に運転を開始して、運転開始から125年以上経った今でも、現役の発電所として電気を送り続けています。
「最長、最初」のオンパレード。
- ねじりまんぽ
インクラインの下にこの「ねじりまんぽ」があります。

ええ?何?ねじり鉢巻きでマンボを踊る?♫♪

いえ、「まんぽ」とは「トンネル」のことで、「ねじりまんぽ」とは、ねじれのあるトンネルと言う意味で、上にあるインクラインと斜めに交わる道路に合わせて、トンネルも斜めに掘られるとともに強度を確保する観点から、内壁のレンガを螺旋状、ねじったように積む工法で作られています。
造りが「ザ・明治」という感じ。
トンネル内にいると、だまし絵のなかにいるようで、身体が自然と傾きます。
トンネルは、中国語で、
隧道suìdào,隧洞suìdòng;地道dìdào;[鉱山・軍事用]坑道kēngdào;[山の]山洞shāndòng.
トンネルを抜ける→穿过隧道.
列車がトンネルに入った→列车进山洞了.
トンネルを掘る→挖wā隧道.
海底トンネル→海底隧道.
野球のトンネルは、
(没有接住的)球从两腿中间滚过(méiyou jiēzhù de)qiú cóng liǎngtuǐ zhōngjiān gǔnguò.
大事なところでトンネルをしてしまった→在紧要关头时(失误)让球从两腿中间滚过。
私は高校の時に少しソフトボール部に入っていて、守備はサードでしたが、いつも「トンネル」ばかりで、レギュラーにはなれませんでした。
普通の道にニワトリ出現!
2021/04/21
京都、東山の日向大神宮へお参りの途中、
道端で、二羽のニワトリが!
「うらにわには にわ にわには にわ にわとりがいる=裏庭には二羽、庭には二羽、ニワトリがいる」という早口言葉がありますが、
庭ではなく、「公道」に二羽。
動画をご覧ください。
ニワトリもコロナ疲れで、散歩しに出てきたのでしょうか。
早口言葉はの中国語は‟绕口令ràokǒulìng”と言います。
‟绕”は、
「巻く、巻き付ける、からみつく」
「ぐるぐる回る」
「回り道をする、迂回する、避けて通る」
「(頭が)こんがらかる、混乱する、混乱させる」
という意味がありますが、
舌がぐるぐる回って、口がこんがらがるから‟绕口”と言うのかも。
ニワトリが市内の普通の道にいて、ビックリで
一时绕住了。Yìshí ràozhù le.
ふいに頭がこんがらがりました。
デカデカ「ジャンボたけのこ」!!
2021/04/20デカデカ「ジャンボたけのこ」!!
特大‟竹笋”tèdàzhúsǔ!!

2メートル以上あります。
これは、もう「たけのこ」ではないかもしれません。
「竹のこども」でしょうか。
たけのこが付くことわざといえば、「雨後のたけのこ」
雨あがりに筍が次々に出てくることから、物事が相次いで出てくる同じようなことが次々と起こることのたとえですね。
中国語は、‟雨后春笋yǔhòuchūnsǔn”
意思是指春天下大雨后发出来的竹笋,而且一下子就长出来很多。比喻新生事物迅速大量地涌现出来。
Yìsi shì zhǐ chūntiān xià dàyǔ hòu fāchū lái de zhúsǔn,érqiě yíxiàzi jiù cháng chūlái hěn duō。
Bǐyù xīnshēng shìwù xùnsù dàliàng de yǒngxiàn chūlái。
春に大雨が降って出てくるたけのこを指し、それが一気にたくさん出てくるという意味。新しい事物が早く大量に現れることのたとえ。
「新しい物が早く大量に現れる」、どんなものがあるか考えました。
私の場合「顔のシミ、シワ」あ〜キョーフ!
「シナチク」と「モクレン」の関係は?
2021/04/19昨日、たけのこをいただきました。
たけのこをいただいたのは、今年になって3回目なので、今回は違う料理にしたくて、「シナチク」の作り方を教えてもらいました。
たけのこを茹でてから、
細切りにし
ゴマ油で炒めて
中華味の素を加え
醤油と酒で味を調整して
出来上がり!!!
上に少しごまをすりました。
(お世辞を言ったりおべっかを使ったりしての、ではないですよ。ちなみにその意味での中国語は‟拍马屁pāi mǎpì”)

どれどれ、味見。尝一尝。 cháng yi cháng
うん、おいしい!不错,好吃! búcuò,hǎochī
写真はその「シナチク」と、一緒に頂いた「菜の花」をおひたしにしたものです。
「たけのこ」は、中国語で‟竹笋zhúsǔn”
「シナチク」とは正確には、
麻竹(マチク)を茹でて塩漬けにして乳酸発酵させから乾燥させ、さらに水で戻して調味したものをいうらしいので、
今回作ったのは「シナチク」とは言えないかもしれませんが、作るのが簡単でとってもおいしかったです。
「シナチク」は中国語で‟玉兰片yùlánpiàn”
‟玉兰”といえば、連想するのが‟玉兰花”、「モクレン」です。
「シナチク」と「モクレン」、同じ‟玉兰”が付くので、調べてみると、やはり関係がありました。
玉兰片是一道色香味俱全的名菜。
Yùlánpiàn shì yídào sè-xiāng-wèi jùquán de míngcài。
用鲜嫩的冬笋或春笋,经加工而成的干制品,由于形状和色泽很像玉兰花的花瓣,故称“玉兰片”。
Yòng xiānnèn de dōngsǔn huò chūnsǔn,jīng jiāgōng ér chéng de gàn zhìpǐn,yóuyú xíngzhuàng hé sèzé hěn xiàng Yùlán huā de huābàn,gù chēng “yùlánpiàn”。
訳文:
シナチクは色、香り、味がそろった有名な料理です。
柔らかい冬たけのこや春たけのこを、加工して作った乾製品で、形と色あいがモクレンの花びらに似ているため、「モクレン片」と呼びます。
ラーメンの上にのっている「シナチク」ですが、「モクレン片」というとなにかちょっとステキですね。
上生菓子を作りました
2021/04/18私の父は和菓子職人です。
若い時は京都の和菓子店数軒に勤め、修業を重ね、私が小学校の低学年の時に独立しました。
和菓子全般なんでも作れるそうですが、商売としては主に落雁や生砂糖(きざとう、工芸菓子に使われるお菓子)などの干菓子を作っていました。
今年84歳になりましたので、もう今は営業していませんが、今回、上生菓子を作っているところを撮影して動画や写真に収めようということになり、「撮影大会」を行いました。
これが、まず一つ目に作った「菜の花」です。

お茶は私がたてましたよ〜。撮影は妹です。
白あんなどの材料から「生地」を作り、そして、このように「とおし」を使います。

お箸でつまんで付けていきます。

京都は和菓子のふるさとです。
京都市のホームページにこのような記載がありました。
「お茶とともに菓子を味わい,季節を感じ,コミュニケーションを楽しみ,心をつなげる。京都で育まれた菓子の文化が未来へとつながっていくよう「京の菓子文化−季節と暮らしをつなぐ,心の和(なごみ)」を“京都をつなぐ無形文化遺産”に選定する。」
和菓子についての中国語の一言
根据历史记载,我们所知晓的日本茶道文化,是由当时日本的遣唐使,将中国唐代的饮茶习惯带回日本的,其中包括了茶道文化和糕饼技艺,都深深的受到日本贵族阶层的喜爱。
Gēnjù lìshǐ jìzǎi,wǒmen suǒ zhīxiǎo de Rìběn chádào wénhuà,shì yóu dāngshí Rìběn de qiǎn Táng shǐ,jiāng Zhōngguó Tángdài de yǐnchá xíguàn dàihuí Rìběn de,qízhōng bāokuò le chádào wénhuà hé gāobǐng jìyì,dōu shēnshēnde shòudào Rìběn guìzú jiēcéng de xǐ'ài.
訳文:
歴史の記録によると、私たちが知るところの日本の茶道文化は、当時日本の遣唐使が、中国唐代のお茶を飲む習慣を日本に持ち帰ったもので、その中に茶道文化と菓子の技が含まれており、日本の貴族階層に深く愛されました。
何はともあれ「久しぶりに白衣を着た」とご満悦

-
 【中国語文法】初心者が最初につまずく「了」の使い方|コツを押さえて話せる中国語へ
【中国語文法】初心者が最初につまずく「了」の使い方|コツを押さえて話せる中国語へ大家好、みなさん、こんにちは。
【中国語文法】初心者が最初につまずく「了」の使い方|コツを押さえて話せる中国語へ
【中国語文法】初心者が最初につまずく「了」の使い方|コツを押さえて話せる中国語へ大家好、みなさん、こんにちは。
-
 中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その1
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その1大家好、みなさん、こんにちは。
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その1
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その1大家好、みなさん、こんにちは。
-
 中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その2
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その2大家好、みなさん、こんにちは。
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その2
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その2大家好、みなさん、こんにちは。
-
 中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その3
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その3大家好、みなさん、こんにちは。
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その3
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その3大家好、みなさん、こんにちは。
-
 中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その4
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その4大家好、みなさん、こんにちは。
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その4
中国語初心者が最初に覚えるべき50フレーズ!二条城観光で実践できる簡単会話その4大家好、みなさん、こんにちは。