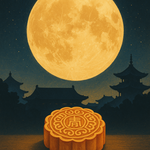- ホーム
- ブログ
ブログ
桜咲く六角堂
2022/03/28桜咲く六角堂
先日金曜日、授業が終わった後に皆さんと一緒に桜が咲く六角堂に行きました。
まだ満開には数日ありそうですが、花の咲いている一角は更に明るいように感じました。
桜は目も心も楽しませてくれますね。
そして、ここで中国語ミニツアーレッスンを行いました。
混同しやすいイディオムを、目の前に有る物を使った文章で練習しました。

お堂の前にこのような旗が何本も立っています。
旗に描かれているのは聖徳太子。
この六角堂は聖徳太子によって建てられました。
そのいきさつは・・・
聖徳太子は四天王寺を建てるため、木材を探しにこの地にやってきました。
そしてちょっと池で身を清めようとして、ずっと持ち歩いていた小さな仏像を木に掛けました。
するとその仏像が、この地にとどまって人々を救いたいと太子に告げて動かなくなりました。
そこで聖徳太子は六角形の御堂を建てて仏像を安置したと言われています。
六角堂のすぐそばに池坊
六角堂の北側には聖徳太子が沐浴したとされる池の跡があります。
この池のそばには僧の住い(住坊)があったため、そこに住んでいた住職を次第に「池坊」と呼ぶようになりました。
聖徳太子に仕えた小野妹子が出家した後ここに住んだということです。
中国語では↓↓
六角堂的北边,保留着一处据传是圣德太子曾沐浴过的水池遗迹,
而在这个水池旁曾有僧侣的住处(住坊),于是居住于此的住持逐渐被称为“池坊”。
曾侍奉于圣德太子的小野妹子出家后据说就居住于此。
住職の「池坊」は、仏前に花を供え、それにさまざまな工夫を加えて「いけばな」に発展しました。
六角堂にはこの他にも歴史的文化的に見どころが満載で、それがぎゅっと凝縮された所です。
『京都を巡る中国語ツアーレッスン』に「六角堂編」も作りたいと思います。
乞うご期待。。
「さくらの日」
2022/03/27「さくらの日」
京都地方気象台は先日3月24日、 京都でさくらが開花したと発表しました。
例年に比べて2日早く、去年に比べて8日遅い開花だそうです。
そして今日3月27日は「さくらの日」
日本さくらの会が制定した記念日で、
3×9(さくら)=27の語呂合せから、3月27日が「さくらの日」となったとか。
季節を表す七十二候で言えば、ちょうど昨日から『桜始開(さくらはじめてひらく)』(桜の花が咲き始めるという意味)に当たります。

さくらは咲いてから散るまで、わずか7日間。そのため、「花七日」とも呼ばれます。
中国語では↓↓
樱花自开花至花残只有七天,因而也有称作‟樱花七日”的说法。
「花七日」(はななぬか)、盛りの短くはかないことのたとえですね。
京都にはさくらのきれいなところがいっぱい。
散らないうちに春を感じにお出かけを。
どうぞコロナ感染対策は十分に!
京都の地名「帷子の辻」読めますか?
2022/03/26帷子ノ辻の由来
京都にはなかなか読めない地名がありますが、「帷子ノ辻」もそのひとつです。
読みかたは、「かたびらのつじ」

京福電鉄(通称・嵐電)の駅に「帷子ノ辻」という駅があります。
この近くに大映の京都撮影所や、現在も「大映通商店街」があり、
この大映通と三条通が交わる辺りに、この「帷子ノ辻」駅があります。
「帷子」とは、夏の着物の一種ですが、地名の由来についてどんな物語があるのでしょうか・・・
平安時代初期、嵯峨天皇の皇后であった橘嘉智子(たちばなの かちこ)は、仏教の信仰が厚く、多くの功績がありました。
この皇后、伝説によると、絶世の美女!
修行中の若い僧侶たちでさえ心を動かされるほど。
こうした状況に皇后は、一体どうすれば、仏教の教えである『諸行無常』の真理、「この世は無常であり、すべてのものは移り変わって、永遠なるものは一つも無い」ということを、人々に告げられるかずっと考えていました。
それならば自らの身をもってそれを告げようと、
自分が死んだあと、亡骸は埋葬せず、どこかの辻に打ち棄てて下さいと遺言しました。
そして皇后の送葬の時、棺を覆った帷子(絹または麻糸で織った夏の着物の一種)が、この辻のあたりで風によって飛ばされ舞い落ち、皇后の遺体はこの辻に遺棄されました。
遺体は日に日に腐り、かつての絶世の美女も醜く無残な姿で横たわり、白骨となって朽ち果てました。
人々はその様子を見て世の無常を心に刻み、僧たちも妄念を捨てて修行に打ち込んだといいます。
皇后の遺体が置かれた場所が、すなわち「帷子辻」と呼ばれた場所だということです。
中国語で要約すると↓↓
平安时代,一个信奉佛教的美貌皇后,为了唤醒世人,宣扬“世事无常”的佛法,留下遗言说,自己死后不要埋葬,而要抛弃在十字路口,就这样被野兽和乌鸦啃噬。皇后尸骨被放置的地方,后来被称作——帷子辻。
点心の由来とは
2022/03/25点心の由来
中華料理の軽食、「点心」、おいしいですね。
そもそも‟点心 diǎnxin ”とは
①]間食として食べる物:菓子・ケーキなど
②軽食(麺類など)
③デザートまたは料理の中間に出される軽い箸休めに相当するもの

「点」は、中国語で、「少し、少量」
「心」は、「感情.気持ち」という意味を表し、
点心は、その字のとおり読むと、「少しの気持ち」
すなわち、「わずかながら感謝の気持ち」という意味に解すことができます。
伝説によると、東晋の時代にある名将が、兵士たちが日夜戦場で戦い、勇敢に敵を倒し、戦果を上げる姿に感動し、
「点点心意」(わずかながら感謝の気持ち)を込めて、みんなの好きなおいしいお菓子を焼いて前線に送り、兵士たちをねぎらうように命じました。
それ以来、「点心」という呼び名が広まり、現在に至っています。
中国語では↓↓
相传东晋时期一大将军,见到战士们日夜血战沙场,英勇杀敌,屡建战功,甚为感动,
随即传令烘制民间喜爱的美味糕饼,派人送往前线,慰劳将士,以表“点点心意”。自此以后,“点心”的名字便传开了,并一直延用。
東晋とは4世紀の初めに建てられた王朝ですから、随分前から「点心」があったのですね。
それにしても、やさしいええ上司やなあ~~
創作「水ようかん」
2022/03/24創作「水ようかん」
冷蔵庫に、こしあんがあったので
水ようかんを作りました。
寒天を一晩水に浸けて戻して作るのはちょっと面倒・・・
簡単にゼラチンを入れてみました。
でもゼラチンの量が少なくてあまり固まらず、包丁で切ることができませんでした。
それならばとスプーンですくってガラス容器に入れて、上にくるみを飾りました。
するとちょっとおしゃれにできました。

砂糖は全く加えずあんの甘さだけで
ちょうど程よい甘さ加減になりました。
「ようかん」は漢字で「羊羹」と書きますね。
羊羹の元々の意味は・・・
羊羹(ようかん)は中国発祥で、羊肉を煮こんだスープを、冷やしておかずにしたのが始まりです。
その後、禅宗とともに日本に伝わり、僧侶は肉を食べなかったため、小豆や小麦粉や葛粉を混ぜて蒸したことから、羊羹は日本では次第に豆類を使ったゼリー状の食べ物に進化していきました。
中国語では↓↓
羊羹起源自中国,最早是用羊肉来熬制的羹,冷却成冻以佐餐。
其后随禅宗传至日本,由于僧人不食肉,于是便用红豆与面粉或者葛粉混合后蒸制,故羊羹在日本慢慢演化成为一种以豆类制成的果冻状食品。
羊羹の「羹」は、中国語でも、とろりとした濃いスープのことです。
「羊の濃いスープ」、羊羹で元々の呼び名がそのまま残っているのはおもしろいですね。
-
 中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統
中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五
中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統
中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五
-
 速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法
速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法みなさん、こんにちは。 大家好!先日、中秋節に関する中国語の音声を用意
速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法
速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法みなさん、こんにちは。 大家好!先日、中秋節に関する中国語の音声を用意
-
 中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現
中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を勉強していて
中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現
中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を勉強していて
-
 中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?
中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?みなさん、こんにちは。 大家好!先日、テキストに「风
中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?
中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?みなさん、こんにちは。 大家好!先日、テキストに「风
-
 中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社
中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社みなさん、こんにちは。 大家好!先日、金曜クラスの受講者のみなさんと一緒に、
中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社
中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社みなさん、こんにちは。 大家好!先日、金曜クラスの受講者のみなさんと一緒に、