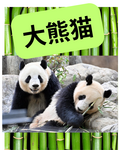京都「太秦(うずまさ)」の由来
「太秦(うずまさ)」の由来

京都には簡単に読めない地名が多々ありますが、「太秦(うずまさ)」もその一つ。
平安時代初期に編集された数少ない書物の中に、『新撰姓氏録』という記録がありますが、
これはその当時近畿に住んでいた氏族の姓および出自等が書かれている氏族名鑑です。
その中の渡来および帰化系氏族のうち約3分の1の多数を占める「秦氏」の項によれば、
中国・秦の始皇帝13世孫、孝武王の子孫にあたる功徳王という人が、仲哀天皇の時代に一族を連れてやってきて、
また融通王という人が応神天皇の時代に、秦氏を引率してやってきて帰化しました。
高度な文明を持つ渡来人は、度重なる国内の戦争や文化交流の広がりによって日本に移住することが多く、農耕技術などの農耕文明、土木建築技術、土器焼成、鉄鍛造、機織りなどの技術を伝えました。
渡来人通常是因国内战争频繁或随文化交流传播而移居日本,这些拥有高度文明的渡来人传入诸如农耕技术、土木建筑技术,以及烧制陶器、锻铁、纺织等农业文明。
その後秦の民はばらばらに散らばっていて、こき使われていました。
そんな状況を、秦酒公(はたのさけきみ)が嘆いて、天皇に訴えたところ、
天皇は、訴えを聞き入れて「秦の民は秦酒公のところに集まれ~」と詔を出したのです。
秦公酒はたいそう喜んで、感謝の気持ちを表し、絹織物をうず高く積んで天皇に献上しました。
天皇は、これらの絹織物は肌膚(ハダ)に温かだとおっしゃって
その時に「波多(ハダ)」の姓を賜ったとされています。
献上された絹織物がうず高く積まれたので、
「禹都万佐(うずまさ)」という号を賜り、後に「太秦」の字をあてたということです。
また、漢字については聖徳太子の「太」と秦氏の「秦」をくっつけたという説もあるそうです。
遠い昔の話が、今も地名として残っていて、この地でそんなことがあったのかと当時の人々に想いを馳せると、歴史の息吹を感じておもしろいですね。
-
 中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
-
 中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
-
 【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って