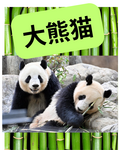こうして話そう!中国語
こうして話そう!中国語
昨日の授業では、会話の練習をたくさんやりました。
着ている服についてや、京都に来て何年になる、といった自分に関する身近な話題です。
問と答え、そこからさらに会話が弾みました。
頭の中で訳さないでください
中国語で何かを伝えようと言葉にするときの注意点として、いつもお伝えしているのが「頭の中で訳さないでください」ということです。
中国語と日本語の語順は異なります。
中国語は語形の変化がないので語順のみが文法的機能をもち、句や語が並ぶ順番がとても大事です。
日本語の文章を中国語の単語に置き換えるだけでは通じなかったり、全く違う意味になったりします。
たとえば「我吃飯」(私はご飯を食べる)が「飯吃我」となると、ご飯が私を食べる、となり、私がご飯に食べられるホラーになってしまいます。
中国語を話すときは、パチッと「中国語脳スイッチ」をいれて、日本語に引きずられないようにすることをおすすめします。
話すときのプロセス
ではそもそも「ことば」を話すってどういうこと?
何語であろうと何かを伝えようとするとき、まず伝えたいメッセージが浮かびます。この時はまだ「ことば」ではなく考えです。
次にそれを「ことば」に変えていきます。単語や文法を選んで組み立てます。そのときに母国語の日本語なら何の苦労もいらないのでしょうが、中国語を話すとなると、今まで習ったことを頭の引き出しからとりだして、文法にも気を付けながら構築するのですから大変です。引き出しの奥深く眠っていて全く出てこないことや、近くにあるのに隠れていてなかなか出てこないこともあります。
さらに、その組み立てた「ことば」を唇・舌・歯・肺などの発声器官を使って音声として出していきます。発声時、有気音や無気音、巻舌音、そして声調にも気を付けて言わなければなりません。
教室ではどんどん恥と汗をかいて
このような複雑でたいへん難しくみえるプロセス・・・・・・・
はじめは間違って当たり前、頭の中をグルグル検索中で時間がかかってもいいのです。
「間違うと恥ずかしい!」、いえいえ間違って恥かいたことほど印象深く残り、それ以降はもう間違いません。
そして言うのに時間がかかってもいいのです。すぐに得た答えはすぐに忘れがちになります。「え~と、え~と」と引き出しから苦労して自分で出すと次に出すときは容易に取り出せるものです。
教室ではどんどん恥かいて汗かいてください。
そうすることできっと上手になります。
私はみなさまのレベルアップのため全力で当たります。

-
 中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
-
 中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
-
 【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って