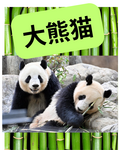小正月の行事を中国語で
昨日は小正月
「小正月」って?「小」があるのなら「大」も「中」もあるの?
「大正月」は元日を中心とする7日までの松の内を指し、
「小正月」は15日前後の二番正月を意味し、
「中正月」はどうやら無いようです。
「中」は生中(ビール)の「中」?!?生中は季節がまだ早い……
それはともかく、「小正月」の昨日、各地で多種多様な行事が行われました。
粥占(かゆうら・かいうら・よねうら)
粥占はおかゆを炊いて、この1年の吉凶を占う行事です。
粥占は各地の神社で祭礼として行われます。
多くの場合は小正月に神にあずき粥を献上するときに、天候や作物の豊凶などについて占います。
占いかたにはいくつか種類がありますが、一般的には煮え上がったお粥のなかへ棒を入れてかき回し、棒についた米粒の数で占います。
そのほかにも、青竹を12本入れてひと月ごとの吉凶を占うものや、お米と小豆(あずき)と竹筒を一緒に炊いて、竹筒に入った小豆の数で吉凶を占うものもあります。
たとえば、京都府亀岡市千歳町の出雲大神宮でおこなわれる粥占祭(よねうらさい)では、毎年1月15日に小豆を混ぜた米を早生、中生(なかて)、晩生(おくて)を表す3本の竹筒とともに釜で炊きます。
ここでは筒に入った小豆が少なく、米が詰まっているほど豊作としています。
見に行ってみようと思いましたが、この行事、朝7時から始まるとのことであきらめました。(亀岡まではちょっと時間がかかるのでそんな早く起きられな~い)
小豆粥(あずきがゆ)
小豆(あずき)の赤い色には、昔から邪気を払う力があると考えられ、
小正月の1月15日に邪気を払い、この1年の健康を願って小豆粥を食べる風習があります。
六朝時代(西暦220年 – 西暦589年)、中国の南部では、1月15日に小豆粥を食べたそうです。
これが日本に伝わって1月15日すなわち小正月の朝に小豆粥を食べるようになったとか。
1月15日の朝に「小豆粥」を食べます。
これは中国発祥の習慣で、
小豆粥を炊いて疫病や邪気を払い、 無病息災を祈願します。
中国語意訳:
在1月15日早上吃“红豆粥”,
这是源自中国的风俗,
煮红豆粥以除疫病,除邪气,祈求无病消无灾。

左義長(さぎちょう)「どんど焼き」
左義长(咚咚烧)
左義長(さぎちょう)は、お正月飾りや書き初めを集めて燃やす行事のこと。
燃やしたときの煙とともに年神様が天上に帰るとされ、その火でお餅を焼いて食べることで万病を防ぐとされています。
また左義長は、「どんど焼き」「どんど」などと、地域によってさまざまな呼びかたがあります。

このように小正月には昔から行われている色々な行事があります。
昔も今も、日本でも中国でも、時代やところが変わっても「疫病退散、無病息災」は変わらないようですね。
-
 中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
-
 中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
-
 【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って