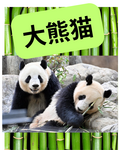京都、勝竜寺城 光秀の逸話
京都長岡京「勝竜寺城公園」を引き続き紹介します。


1582年、本能寺の変後、明智光秀と羽柴秀吉が決戦に臨んだ天下分け目の「山崎勝竜寺城の合戦」では、この一帯が戦場となりました。
戦局は短時間で決し、敗れた光秀は勝龍寺城へ逃げ込み、最後の夜を過ごしています。
(勝竜寺城公園のパンフレットより)
光秀は再起を図るため、落ち延びましたが、その途中で落命しました。
命を落とした竹藪は今の山科区小栗栖になるそうで、マップで調べてみると勝竜寺城から徒歩2時間半のところです。享年55歳。
しかしながら、こんな話もあります。
江户中期明和年间(1764-1772)神泽贞干所著的随笔《翁草》中有关于光秀的一段奇异的描述。
死在小栗栖的是光秀的影武者,光秀本人逃到了美浓山县郡美山中洞。
这个传说看似荒诞不经,不过,主要一点是光秀没有死在山崎合战中。
确实,仔细分析山崎合战的过程、逃离胜龙寺城、然后在小栗栖受山民袭击这一连串的变化,能发现很多难解之处,
因此生出了光秀生存说。
事实上,比睿山有石灯笼上刻“庆长二十年二月十七日,奉寄进,愿主光秀”。
庆长二十年(1615),正是大坂冬之阵结束,大坂城壕被填,丰臣家濒临灭亡的时候,自本能寺之变发生已二十三年。
这个“光秀”是活下来的明智光秀吗?
丰臣家灭亡,德川一统天下的时代来了——光秀认识到这一点,就大胆地以“光秀”之名供奉石灯笼,向世人宣布他还活着。
訳文:
江戸時代中期(1764〜1772年)に神沢貞観が書いた随筆「翁草」には、光秀に関する不思議な記述があります。
小栗栖で死んだのは光秀の影武者であり、光秀自身は美濃山の郡山中村の洞穴に逃げ込んだのです。
この伝説は荒唐無稽に思えますが、重要な点は山崎の戦いで光秀は死んでいないということです。
確かに、山崎の戦い、勝竜寺城からの脱出、そして小栗栖での山人の襲撃という経過を詳細に分析すると、
光秀生存説を生み出す不可解な点がいくつも出てくるのです。
実際、比叡山には「慶長20年2月17日、願主光秀、寄進」と刻まれた石灯籠があります。
慶長20年(1615年)、大坂冬の陣が終わって大坂城のお堀が埋められ、
豊臣家が滅亡の危機に瀕していた時、本能寺の変から23年経っていました。
この「光秀」は生き残った明智光秀なのでしょうか?
豊臣家が滅び、徳川が天下統一する時代が来ました。
それを知った光秀は、思い切って「光秀」の名で石灯籠を献上し、
自分がまだ生きていることを世間に知らせたのでした。
へえ〜〜そんな話もあるのですね
それからこれはお庭にある細川忠興と玉(ガラシャ)の像

明智光秀の娘、玉が勝竜寺城の細川忠興のもとへ輿入れしたエピソード再現する「長岡京ガラシャ祭」は毎年11月第2日曜日に催されます。
また、これは庭にある「ガラシャおもかげの水」という立て看板

「地下水100%の水道水です。ご自由にお飲みください。」と書いてありますが、このコロナの時期で飲用禁止になっていました。
建物の2階は「歴史ミュージアム」になっていて、
甲冑の展示や、勝竜寺にゆかりの深い明智家と細川家の人々の生涯が紹介されています。
一番奥にある大きなモニターで流されているビデオはとても分かりやすかったです。
とても見る価値のあるお城公園です。
-
 中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
-
 中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
-
 【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って