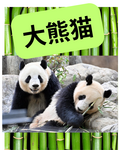京都五山送り火、今年は点火わずか
昨日16日夜、京都では「京都五山送り火」が行われました。
新型コロナの感染防止のため、規模を大幅に縮小しての送り火でした。
大文字山(如意ヶ岳)の「大」の字は、火床が75カ所ありますが、そのうち中心と端にあたる所の6ヶ所だけしか点火されませんでした。
鳥居も2カ所だけ、妙法もそれぞれ1カ所だけでした。
さみしいですが、今は仕方がありません。
例年の大文字山

大文字五山送火,也叫五山送火,是每年8月16日在环绕京都盆地的群山的半山腰上,用篝火描绘出巨大文字的活动。
Dà wénzì wǔshān sòng huǒ,yě jiào Wǔshān sòng huǒ,shì měinián 8 yuè 16 rì zài huánrào Jīngdū péndì de qúnshān de bànshānyāo shàng,yòng gōuhuǒ miáohuì chū jùdà wénzì de huódòng.
訳文:
大文字五山送り火は、五山送り火とも呼ばれ、毎年8月16日に京都盆地を囲む山の中腹で行われ、焚き火で巨大な文字が描かれる行事です。
この送り火はお盆の行事で、先祖の霊を安らかに冥土へ送る意味があります。
この大文字の起源は、
平安時代初期、大文字山(如意ヶ岳)山麓の浄土寺が火事になり、その時本尊の阿弥陀仏が山の頂に上って光明を放ち、その光明をもとに空海(弘法大師)が「大」の字にしたと言う説や、
銀閣寺から大文字山(如意ヶ岳)が銀閣寺領だったと言う資料が発見されたので、室町時代中期に足利義政が始めたと言う説もあり、
如意ヶ岳に刻まれた「大」の字が、銀閣寺と同じ派の相国寺(御所の北側)の方を向いていて、足利将軍との関わりを示し、この説が有力視されているそうです。
夜、山の中腹にポツンポツンと灯る火を、弘法大師と足利義政が見ればどう言うでしょうかね。
-
 中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
-
 中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
-
 【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って