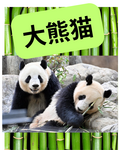土用の丑 鰻で中国語まちがい探し
土用の丑
鰻を食べてこの暑い夏を乗り切ろう!

どうして土用の丑の日に鰻を食べるようになったかについては、「江戸時代の平賀源内が発案した」という説が最もよく知られています。
平賀源内の知り合いの鰻屋は、商売がうまくいっていませんでした。
そこで、夏に売れない鰻を何とか売るため、平賀源内のところに相談に来たところ、平賀源内は、「本日丑の日」と書いて店先に貼ることを勧めました。
すると、その鰻屋は大変繁盛したのです。その後、他の鰻屋もそれを真似るようになり、土用の丑の日に鰻を食べる風習が定着したというもの。
鰻自体は江戸時代よりもっと前から食べられていて、昔の文献や木簡などの資料、出土品に基づいた研究からも、鰻は古代から食べられていたことが分かるそうです。
奈良時代の『万葉集』には、鰻が既に夏の栄養源とされていたと伝える歌などがあり、そんな前から鰻が食べられているとは驚きです。
当然、当時は中国産も台湾産もなかったでしょう。
まちがいさがし
ここで、もう、まちがえない!実践チュウゴクゴ(40)
中国語の表現でまちがいやすいところの解説をしています。
文中どこがおかしいのか、先ず考えてみてください。
正解したあなた・・・・・・・さすが!!!
分からなかったあなた・・・・・・・これをきっかけに覚えて下さいね。
*今日の文章*
鳗鱼是比较昂贵的食材,只要日本的贵族才能享用这种昂贵、奢侈的美食。
「鰻は比較的高価な食材で、日本の貴族だけがこの高価で贅沢なグルメを楽しむことができました。」と言いたいのですが・・・

さて、どこが間違っているでしょう?
よくよく、見てくださいね。まちがいは、たった一字なのです。
ただ…だけが…だ、というときは、
‟只有”
を使って、後に“才cái”を置いて呼応させることが多いですね。
まちがいの今日の文章では、‟只有”とするべきところに‟只要”が使われています。
正しくは
鳗鱼是比较昂贵的食材,只有日本的贵族才能享用这种昂贵、奢侈的美食。
Mán yú shì bǐjiào ángguì de shí cái,zhǐyǒu Rìběn de guìzú cáinéng xiǎngyòng zhè zhǒng ángguì、shēchǐ de měishí.
「鰻は比較的高価な食材で、日本の貴族だけがこの高価で贅沢なグルメを楽しむことができました。」
‟只要”は、〔必要条件を表す〕・・・さえすれば、・・・でさえあれば、という意味で、“只要……就jiù……”の形でよく使われますね。
一字違いで大違いなので気を付けましょう。
例文の続き・・・
后来鳗鱼被广泛的养殖,产量高了,普通的群众也能消费得起。
Hòulái mán yú bèi guǎngfàn de yǎngzhí,chǎnliàng gāo le,pǔtōng de qúnzhòng yě néng xiāofèi děi qǐ
その後、鰻の養殖が盛んになり、大量に生産されるようになると、一般の人にも手が届くようになりました。
「手が届く」けど、やっぱりお高いですよね。
-
 中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
-
 中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
-
 【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って