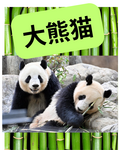夏越の祓に、おやつの水無月
夏越の祓(なごしのはらえ)
今日で6月も終わりです。
一年の折返しに神社で行われる季節の行事が、夏越の祓(なごしのはらえ)で、
この半年分の穢れを落として、残りの半年の無病息災を祈願して、「茅の輪くぐり」をしますね。
「水無月(みなづき)」
京都では、この時期に「水無月(みなづき)」を食べます。
これは、昔、春から秋に氷を作る技術が無かったので、冬場にできた天然の氷を溶けないように、「氷室」という山の洞窟や地面に掘った穴に入れて保管し、夏になると出してきて食べて暑気を祓うという、宮中の行事に由来しています。
冷蔵庫の無かった時代、天然のものを保管するしかありません。
ですから、夏場の氷はとても貴重品で、長らく朝廷や将軍家など一部の権力者のものでした。
明治以降、氷のかけらを表す三角形の「ういろう」に、魔よけとなるの赤い小豆を載せた今のような形のお菓子を食べる風習になったといわれています。
写真の水無月は、「氷室」ではなく、家の「電子レンジ」で作りました。

「おやつ」とは
この水無月、「おやつ」に、いただくことにします。
でもどうして、「おやつ」と言うのでしょうね。
午後2時から午後4時頃を、八つ刻(やつどき)と言って、江戸時代、この時間に間食をしたことから、間食全般を「おやつ」と呼ぶようになったそうです。
「おやつ 」 は、中国語で、
点心diǎnxin,茶点chádiǎn.など
例文:
このお菓子はとてもおいしい|这个点心很好吃。
このお菓子は何で作ったの|这个点心是用什么做的?
和菓子の中でも「京菓子」は特別
京菓子は、その見た目の美しさと、上品な甘さ加減、季節感たっぷりで、そのお菓子についた名前も楽しめるというものです。
さらに京都の暮らしの中で、季節を彩るお菓子は、お供えやお客さまのもてなし、人生のお祝い事、年中行事などのしきたり、町内の集まりなど、その場に応じて添えられてきました。
茶道のみならず、普段の生活で、京菓子は人の心を表現したり、その場の雰囲気を盛り上げたり、人間関係を円滑にするコミュニケーションの道具として上手に使われてきたのです。
京都にお越しの際は、是非、休憩のおやつに、召し上がってください。
-
 中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
-
 中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
-
 【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って