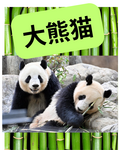威張らない力士

‟摆架子”という中国語をご存知でしょうか?
”摆架子 bǎi jiàzi ”は、「威張る、お高くとまる、見栄をはる」という意味ですね。
‟架子”は、棒状のものが組み合わさってできた支えのことで、棚や台を指します。
例えば
トランクを棚に上げる/把皮箱举起放到架子上。
本棚/书架子などと言います。
そして、”摆”は「並べる、陳列する、(配置を考えて)置く」という意味を表すので、
ええ?棚や台を並べる?
それがどうして「威張る、見栄をはる」という意味になるの????
ということで、‟摆架子”の由来について調べてみました。
中国語の文章があったので、それを訳すと、意外!「相撲」と関係があったのです。
以下は訳した要約文:
中国にも古代には「相撲」がありましたが、後に途絶えてしまいました。
しかし、日本人では「相撲」が残り、国技となって、全世界の興味を引いています。
相撲は体重が数百キロ以上の太った力士の間で行われます。試合前には、足、腰を少し曲げて、頭を上げ、虎視眈々と相手をにらみつけ、その構えた姿、ポーズはとっても恐ろしい!飛びかかられたらひとたまりもないのは言うまでもなく、さっと身をかわされて踏まれても、ぺちゃんこになってしまう。
こうした力士の構えた姿、ポーズの怖さから、中国の古書ではこれを借りて、威勢を誇示することを、‟摆架子”と言いました。”架子”は、「棚や台」のほかにも、姿勢、ポーズ、構えの意味もあるのです。
でも今の日本の力士は、立ち合い前、「威張ったところ」は全くありません。
‟摆架子”の由来が「相撲」だったとは驚きでした。
関連エントリー
-
 中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
-
 中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
-
 【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って