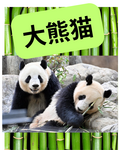お盆の由来(お母さん何悪いことしたの?)
お盆期間、いかがお過ごしですか?
京都では、「六道まいり」や「五山送り火」という風習があるのはご存知の通りです。

お盆の話は、『盂蘭盆経』の中の目連が母を救う話に由来しています。
目連は仏教の始祖――釈迦の弟子で、その母は死後、地獄で苦しんでいました。
目連は釈迦に母を救ってくれるよう懇願しました。
釈迦は、母の罪をあがなうため、旧暦7月15日に10万人の僧侶のために百種類の料理を用意するよう、目連に命じました。
目連は釈迦の教えに従い、「お盆」を設け、最後には母を救い出すことができました。
中国語訳:↓↓
孟兰盆节的故事源于《孟兰盆经》中目连救母的故事。
目连是佛祖释迦牟尼的弟子,他的母亲死后在地狱受苦,
目连求佛祖解救母亲。佛祖命目连在农历七月十五日准备百种食品,供养10万僧众,以赎去母亲罪恶。
目连依照佛祖之言,设“盂兰盆会”,终于使母亲得到解脱。
ちなみに[盂蘭盆会・うらぼんえ]とはインドのサンスクリット語のウラバンナ(逆さ吊り)を漢字で音写したもので、 転じて「逆さまに釣り下げられるような苦しみにあっている人を救う法要」という意味だそうです。
ここで素朴な疑問。
目連のお母さんは地獄で苦しむような、どんな悪いことをしたのでしょうね?
先日の授業で、受講者のみなさんに聞いてみると
・檀家さんにお金を要求した
・お盆期間に食べてはいけないものを食べた
・不倫
との答えが返ってきて、爆笑でした。
関連エントリー
-
 中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
-
 中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
-
 【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って