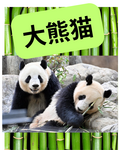京都を巡る中国語ツアーレッスン
京都を巡る中国語ツアーレッスン
昨日は『伏見稲荷大社編』で開催
10時にJR稲荷駅に集合した頃に、ちょうど雨が止みました。

受講生の方は、伏見稲荷大社に来るのが初めてで、熱心に聞いて下さいました。
今回用意した資料は少し難しかったのですが、発音もばっちり!
ご参加ありがとうございました。
ひとつ質問されたのが、「油揚げはどうして稲荷(いなり)というのですか?」
问得好! いい質問ですねぇ。
日本では古くから農耕をしていました。農作物を荒らすネズミはとっても迷惑。そのネズミを好んで食べる狐は人々から崇(あが)められていました。
地域によっては狐の巣穴の前に、狐の好物であるネズミを油で揚げた「ネズミの油揚げ」を置いていく習慣があったそうです。
狐は雑食ですので油で揚げたネズミも食べていたのでしょう。ネズミのから揚げ?こわ~~い
その後、仏教が日本に伝わり、肉を食べたり殺生するのは良くないという思想が広まり、
ネズミを油で揚げた「油揚げ」ではなく、薄切りにした豆腐を油で揚げた「油揚げ」を供えるようになりました。
農業の神様を祀る稲荷神社では狐が神の使いとして祀られています。
狐の好物といわれる油揚げをお供えすることから、油揚げを使った料理を「稲荷(いなり)」と呼ぶようになったのだそうですよ。
中国ではよく野生動物を食べます。
私が留学していた広州は、さすがに「食は広州にあり」と言われるだけあって色々な動物が普通のレストランでも食べることができ、ここは動物園かと思うほどのにおいがしたことが思い出されます。
伏見稲荷大社ではこれも有名ですね。↓

ウズラとスズメの串焼き!ちょっとグロい!?
関連エントリー
-
 中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
-
 中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
-
 【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って