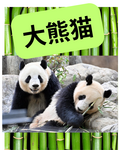花を愛でる
京都駅西口コンコースにお花が飾られていたとの写真を送ってもらいました。
お花があると華やいでいいですね。
写真を見るだけでも、いいですね。

これは「池坊」と書いてあったそうです。
どうして「池坊」というのでしょうか?
こんなお話が載っていました。
聖徳太子は、普段「如意輪観音」を拝んで持ち歩いていました。その観音様は淡路島に流れ着いた観音像でした。
587年、大阪の四天王寺を建てることになって、聖徳太子は材木を探しに、京都盆地にやってきました。
太子がある池で身を清めようと、持っていたその観音様を木に掛けたところ、観音さまが動かなくなり、
「この地にとどまって人々を救いたい」と太子に告げました。
それでその地に六角形の御堂を建てて安置したといわれます。
そのお堂が六角堂。

お堂の北側に池があります。

この建物は「太子堂」
=============================
後に、聖徳太子に仕えていた小野妹子が出家してここに住まれました。
小野妹子と言えば聖徳太子の命で中国に渡った「遣隋使」が有名ですね。
出家した小野妹子はこの六角堂の初代住職として朝夕、仏前に花を供え始め、
これがのちの華道の始まりとされています。
この池のほとりに僧達が寝泊まりする宿舎、すなわち「住坊」があったことから、
池のほとりの「住坊」、
六角堂の住職は「池坊」と呼ばれるようになったといわれています。
いまでも池坊の家元が六角堂の住職を務めていらっしゃるそうです。
六角堂には、先日紹介した「一言地蔵」や、
親鸞聖人像
縁結びの柳の木など
いろいろ見どころいっぱいです。
緊急事態宣言が解除されて、陽気も暖かくなって来た頃、
再びお参りしたいと思います。
もうしばらく、ステイホームで「赏花 shǎng huā」(お花を愛でる)ことにします。
関連エントリー
-
 中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
-
 中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
-
 【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って