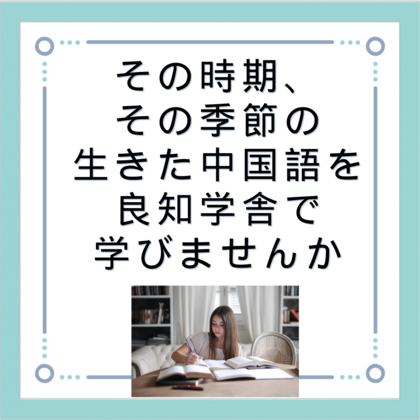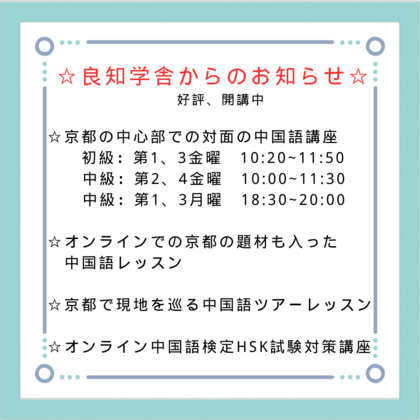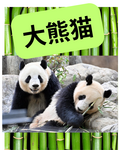京都西院春日神社「若菜祭」で美味しいお粥に舌鼓:粥は中国語でこう言う!
京都西院春日神社「若菜祭」で美味しいお粥に舌鼓:粥は中国語でこう言う!
みなさん、こんにちは。 大家好!
新春の京都・西院に位置する春日神社では、毎年1月7日に開催される「若菜祭」が、参拝者を魅了しています。
本日、私もその雰囲気に浸りながら、春の七草を捧げ、若菜粥をいただく素晴らしい体験をしてきました。
春日神社と「若菜祭」
春日神社は、京都の西院に鎮座する神社で、春を象徴する祭り「若菜祭」が開催されます。
この日、春の七草を神に捧げるとともに、参拝者には特別な「若菜粥」がふるまわれます。
この「若菜祭」は、新しい季節の始まりとともに健康と幸運を祈るもので、多くの人々が訪れています。

「若菜祭」の魅力
若菜祭の特別なポイントは、春の七草をいただくことで、新たな季節の幕開けを感じることができる点です。
参拝者は、花や若菜で飾られた神社の雰囲気に包まれながら、心を清め、新たな始まりへの期待を抱きます。
また、白馬を見ると健康に暮らせるという言い伝えにちなんで、「白馬(あおうま)飾り」があり、これも目を引くポイントの一つです。
これは普段は公開されていなくて、今日特別です。
本殿前のお賽銭箱の後ろに置かれていました。
「若菜粥」の味わい
若菜祭の中心とも言えるのが、「若菜粥」です。
この若菜粥、一杯わずか300円でいただけます。
ご利益があるとされ、その美味しさとパワーを求めて、参拝者たちが長~~~い列を成していました。
春の七草の香りが漂う中、温かい若菜粥を頬張る瞬間は、まさに春の幸せを感じることができます。

若菜粥に込められた思い
- 中国では
「粥」は、中国語では"粥 zhōu"と言います。
”粥”は、生の穀物(例えば米)を長時間煮込んだものを指し、
一度炊いた飯を水でばらして煮たものを、北方では"稀饭 xīfàn"、南方では"泡饭 pàofàn"と言います。
そして「若菜」はいわゆる「七草」のことですね。
七草粥の風習は中国元々は古い習慣であり、6世紀の『荆楚歳時記』に記載があり、
唐代には、「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」と呼ばれるスープを食べ、病気や災厄からの無事を祈っていました。
また、中国古代の官吏の昇進が1月7日に決まるという言い伝えもあり、春の若菜で作ったスープを食べて出世を祈るとされていたようです。
中国は広大な国土を有しており、習慣は変化していくものの、古い習慣が新しい形で継承されていることが見られます。
七草粥は中国では現在「七宝羹」、「七種粥」、「七樣羹」(潮汕地域)と呼ばれており、福建、広東、台湾、湖南、湖北などで今でも食べられているそうです。
- 日本では
日本では春の七草の初めての記録は平安時代にさかのぼり、
また、古書『日本歳事史』には、「地上には七草があり、これを摂取することで魂魄の力が増し、寿命が延びる」と記載されています。
「七草粥を食べると邪気が取れ、万病が防げる」ということですね。
七草粥は始めは宮廷の料理でしたが、江戸時代になると庶民に広がりました。
- 栄養価
科学的な観点から見ると、七草にはβ-カロテン、ビタミンB1、B2、C、ニコチン酸、カルシウム、鉄などが含まれており、
体内の糖質、タンパク質、脂質の代謝を促進し、過食や飲み過ぎによって傷ついた腸胃を修復し、ミネラルを補充する効果があるそうです。
- まとめ
春日神社の「若菜祭」は、春の訪れを感じ、健康と幸運を祈る素晴らしい機会です。
春の七草を捧げ、若菜粥をいただくことで、新たな季節の始まりを心から楽しむことができました。
-
 中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!
中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ
-
 「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2
「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で
-
 中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ
中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン
-
 【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化
【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って